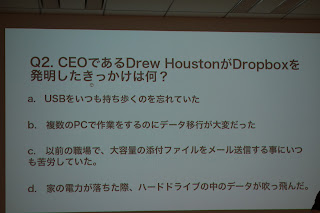毎度どうも! 整理整頓が苦手な管理人です。
とにかく、あちこちお邪魔しては、いただいた書類がデスク周りにてんこ盛り。自分でもどこに何があるのかわからなくなることもしばしば。
PFUのドキュメントスキャナー「ScanSnap iX100」を持っているので、思い出したようにスキャンするんだけど、追いつかない。
どうする、そろそろ自動紙送り機能のあるiX500を買うか? と思っていたところ、PFUからお知らせが。
「10月2日、新商品が出ますよ」
というわけで、発表会に行ってきましたよ!
ScanSnapの歴史とは?
1995年、Windows 95のOSが発表されてから、PCは、より「パーソナル」なものとして各家庭で購入されるようになって、それと同時にプリンターも導入されていった。せっかくだから、スキャナーも買いたいなぁと思っても、なかなか高嶺の花だった、という記憶を持っているインターネット老人会の人もいることでしょう。かく言うわたしも、当時はEPSONにどっぷり浸かっており(Canon派の人もいたけど、なんかカッコつけマンみたいで反発していたw)、EPSONのフラットベッドスキャナー欲しいなぁ、でも6万円かぁ、みたいな感じだった。プリンターと合わせて10万弱! 買えない!
いつしか、複合機が主流になり、スキャナーはより身近なものになっていったけど、コピー機みたいに書類を一枚一枚置いてはスキャンして取り出して、また置いて……というのが面倒で、結局使わなくなったのよね。
だから、次々と書類を手差ししていけば、どんどん読み取ってくれるiX100を手に入れてからというもの、かなり便利に使っていたのよね。それでも溜まるんだけど(笑)。
で!
今ではPFUによるドキュメントスキャナーのシェアは国内トップ。67%なんだそう。ちなみに、世界100カ国の中では50%。それでも充分すごいんだけど。
そして、「2017年7月には、弊社のイメージスキャナー(いわゆる、わたしたちが普通に「スキャナー」と呼んでいる製品)の累計販売台数は1000万台を突破した」とPFU代表取締役社長の半田清さん。1000万台!
プレスリリース:PFUイメージスキャナ全世界累計出荷台数1,000万台を突破
ちなみに、その数に含まれるけど「ドキュメントスキャナーは2018年9月に500万台の大台に達した」と執行役員常務の宮内康範さん。発表会が行われたのが10月2日だから、このタイミングで達成できたのはうれしいだろうなぁ。
PFUの主力製品となったScanSnapシリーズだけど、初号機の販売は2001年から。1983年にはじまったイメージスキャナーの歴史と比べると、ちょうど半々やね。台数も半々か。
でも、最後に出たのがiX500。2012年12月のこと。それから6年も新商品が出ていなかったんですよ! なのに売れているんですよ!
その理由は、世の中の動きとScanSnapの使いやすさにある、と半田さんと宮内さん。
半田さんは、「働き方改革でテレワークへの取り組みが進むにつれ、情報共有は必要不可欠となった。アナログとデジタルの橋渡しとして、ScanSnapは役立っている」と説明。
宮内さんは、「ScanSnapは、ワンプッシュで書類をスキャンできる手軽さをコンセプトに、ワイヤレス化、クラウド活用と時代の流れをキャッチアップしつつブラッシュアップしてきたのが、ロングセラーの秘訣」と言う。
次代のニーズにガッチリ合致した製品、ということなんでしょうな。
そして、満を持しての新商品ですよ!
6年ぶりの新商品ははじめての○○を搭載
新しいScanSnap iX1500は、iX500の流れを汲む据え置き型。ADFで高速スキャン。1分間に30枚、60面を読み込みますよ。利用シーンの動画を見たけれど、速い速い。まあ、渡しが浸かっていたのがiX100だからそう感じるのかもしれないけれど(注:iX500では、25枚50面/分なので、速くなっていることは速くなっている)。それより何より特筆すべきは、ScanSnapシリーズなのに、タッチディスプレイが搭載されたことですよ、奥さん!
あとで宮内さんにお聞きした話では、「ScanSnapはワンボタンがいいんだー!」というこだわりが、開発チームにはあったんだとか。でも、「スマホも出てきたしねぇ。タッチディスプレイは時代の流れなんじゃない?」という声も出てきていて、“Scan”というわかりやすいボタンをディスプレイに表示すれば、これまでの良さも踏襲できるのでは? とのことで、タッチディスプレイをはじめて搭載した機種が世に送り出されることになったようです(非公式情報)。
さて、これが搭載されることで、何が便利になったのか。
スキャン時に、どんな動作をするかというプロファイルを割り当てたアイコンをタッチするだけで、その操作が行えること、ユーザーを最大4人まで切り替えられること、読み取りの各種設定を本体だけで済ませられること、などなど。
プロファイルについて、もう少し説明すると、例えばこれまでのScanSnapでは、細長い紙はクラウド家計簿に、A4サイズの紙はEvernoteに、名刺サイズは名刺管理ソフトに、という具合に自動的に割り振らていたけれど、iX1500では(それができるおまかせスキャン以外に)、いつもは名刺管理ソフトに送る名刺サイズのスキャンデータをEvernoteに送る、とか、いつもはEvernoteに送る書類を「家族で共有するストレージ」に送る、などのコマンドを設定できる。
登録できるプロファイル数は全部で30。最大4ユーザーが1台のScanSnapを使えるので、一人あたり7つ? 残り2個は、じゃんけんで決めて分け合いましょう。
そうそう、これまでScanSnapCloud対応のScanSnapでは、1台ごとに1ユーザーしか使えなかった(使えないというか、ソフトウェアライセンスが一人分しかなかった)んだけど、iX1500では4人まで使えますよ! 一家に一台でOK! もしくは、小規模オフィスなら、一台あれば、事足りる!? iX500とPFUダイレクト価格は変わりがないのに、一人一台じゃなくていいんですか、PFUさん!? と叫びたくなってしまった。太っ腹ですな。
目指したのはストレスフリーな使い心地
開発に携わっていた第一開発部長 大窪伸幸さんによれば、iX500のポイントは以下の3つ。- やりたいことをワンタッチ! 簡単操作のタッチパネルを搭載
- 整理・活用をスマートにアシストする全く新しいソフトウェア
- 洗練されたデザインと、ストレスフリー設計
あ、タッチディスプレイじゃなくて、タッチパネルだった。
もとい。
「1」についてはひとつ前の見出しで説明したとおり。
「2」だけど、新商品の販売と同時に、専用管理ソフト「ScanSnap Home」をMac/Win用にリリース。利用はもちろん無料。っていうか、本体価格に含んでいるのね。
これは、ScanSnapを操作するだけのソフトではなく、これまで“ドライバ”“名刺管理”“ファイル管理・閲覧”“ScanSnapCloud”などに分かれていたソフトウェアを統合した、全く新しいもの。プログラムバーがScanSnapだらけにならずに済むんですのよ、奥さん。
見た目がスッキリするだけでなく、1つのソフトの中で全部できるから、操作もシンプル。
個人的には、ファイル管理機能に期待している。
というのも、スキャンした紙書類はPDFにしたものだけでなく、JPEG保存したものでもOCRが働いて、全文検索の対象になるから。スキャンしたはいいけど、書類が見つからない! というストレスから解放されるんじゃないかなぁと思っている。
紙書類のスキャンが進まないことの理由のひとつに、「目の前から対象物がなくなってしまったら、探しきれないんじゃないか?」という不安があったから。でも、このScanSnap Homeがあれば、スキャンしたほうが検索性が高まる、ということだもんね。これは使うしかない。
あとあと、すごいのは、優れた学習機能。例えば! 「毛糸だま商事」の人と名刺交換をして、OCRが「も糸だま商事」と読み取ってしまった場合、「『毛』だよ、『毛』!」とブツブツ言いながら修正しますよね? で、同じ会社の人と何枚も名刺交換すると、それを何度も修正することになる。イラッとしますよね!?
でも、ScanSnap Homeなら、一度修正すれば「これは『毛』なのか!」と学習してくれ、二枚目以降(二回目以降?)は修正不要。
書類の場合では、自動的に作成されるファイル名が気に入らないとき、一度修正すれば、同様の書類を読み込んでできたファイルの名前が、修正いらずのものになる。例えば、「2018年10月31日【請求書】 請求No.100990」と紙の書類の頭部分に印刷されていて、読み込んでできたファイル名が「20181031_【請求書】100990」になってしまったものを「請求書_20181031_100990」に修正した場合、次からは同じような書類を、それに準じたファイル名に自動的にしてくれる、というわけ。イラッとせずに済む。
大窪さんはこれを「使えば使うほどあなた好みになるScanSnap」と表現していた。やだかわいい。
ちなみに、4人まで使えると書いたけど、ScanSnap Homeは、ユーザーそれぞれのPCにインストールするため、学習情報はユーザー間で共有されることはない。ローカル依存ですな。
これには理由があって「会社でも家でも同じPCを使う場合、同じScanSnapを使うユーザーにその情報が漏れてしまっては、セキュリティ面でよろしくない」から。そりゃそうだ。だから、同じScanSnapで家族それぞれがデータを読み込んでも、読み込んだ情報は家族に漏れることがない。安心・安全。
「3」について。オフィスユースだけでなく、家庭でも使うことを前提にしたデザインだから、とにかく美しい。
まず、カラーがホワイト。そして、背面がすっきり。あれだ、家具で「背面化粧板」とかいうのがあるじゃない。壁にピッタリくっつけないで、間仕切りとしても使えるよ、みたいな。あんな感じの背面なので、家の真ん中に置いておいても全然平気。
ストレスフリーということについては、カバーを開けたらすぐに使えて、待ち時間ゼロ、というところや、読み取り速度など。
まあ、まだ使っていないので、アレですけど、レビューしたいですね。ね!
買える人は買っちゃってください。きっと「買って良かったー」と思うんじゃないかと。そして、部屋が片付きますよ! きっと!
あ、予約は10月2日開始、販売は10月12日から、価格はオープンだけど、PFUダイレクト価格で5万1840円(税込)ですよ!